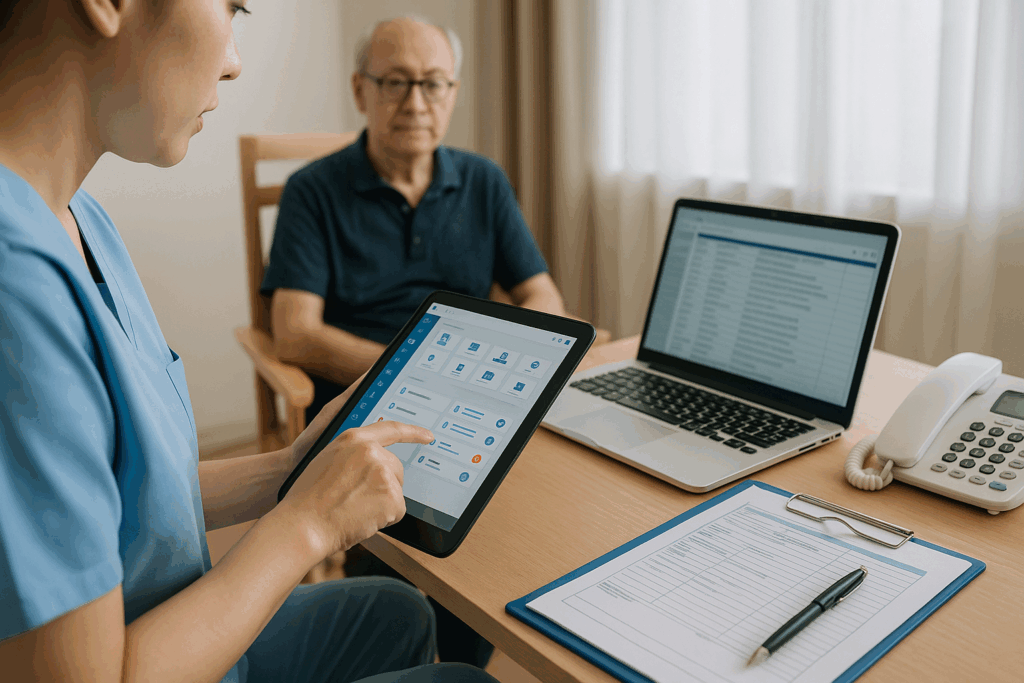
高齢化社会が急速に進む日本では、2025年問題を前に介護業界の人材不足が深刻化しています。
厚生労働省の予測によれば、2025年には約30万人以上の介護人材が不足する見込みです。
この危機的状況を打開する鍵として注目されているのが「ペーパーレス化」による業務効率化です。
膨大な記録業務に追われる介護現場で、デジタル化はどのように進み、どのような可能性をもたらすのでしょうか。
なぜ今、介護業界でペーパーレス化が求められているのか
少子高齢化と人手不足の深刻化
日本の高齢化は急速に進行し、2025年には団塊の世代が75歳以上となり、国民の約5人に1人が後期高齢者になると予測されています。
この「2025年問題」に対して、介護業界では深刻な人手不足が懸念されています。
厚生労働省の予測によれば、2025年には約30万人以上の介護人材が不足する見込みです。
こうした状況下で、限られた人材で効率的にサービスを提供するための業務改革が急務となっています。
働き方改革と業務効率化の必要性
介護現場では記録や書類作成などの間接業務が大きな負担となっており、これらの効率化は働き方改革の観点からも重要です。
介護記録の電子化によって削減された間接業務時間は、利用者へのケアに充てるだけでなく、残業時間の削減や休憩時間の確保にもつながります。
これは介護業界における人材確保や離職防止にとって大きな意味を持ちます。
行政のデジタル推進政策との連動
厚生労働省は「ICT導入支援事業」を積極的に推進しており、令和元年の195事業所から令和3年度には5,371事業所にまで支援が拡大されています。
また、2018年度には行政手続きに必要な文書の簡素化や電子化を目指す改正省令が公表され、2019年度を目途にPC画面での書類確認や、報酬請求・各種申請でのWeb入力や電子申請の導入も検討されています。
こうした国の施策と連動して、介護現場でもペーパーレス化が推進されています。
介護現場の「紙業務」の実態
記録業務:バイタル・日誌・申し送り
介護現場での記録業務は膨大で、特に施設では月に1000枚単位の記録票が発生します。
バイタルサインの記録、食事や排泄、入浴など日常的なケア記録、さらに申し送り事項など、多くの情報を正確に残す必要があります。
これらは従来、紙媒体で記録され、事務所に持ち帰って整理・保管するという手間のかかる作業でした。
訪問介護では、ケアごとに所定の記録書に手書きで記入し、利用者からサインや捺印をもらった報告書を事務所に立ち寄って提出するという流れが一般的でした。
ケアプラン・契約書・給付管理の書類
介護サービスを提供するにあたって必要な書類は記録だけではありません。
ケアプランの作成・更新、契約書類の管理、介護保険請求のための給付管理など、多岐にわたる書類業務が存在します。
これらの書類は正確性が求められるだけでなく、法令に基づいた適切な管理と保管が必要です。
紙業務がもたらす課題(ミス・保管コスト・時間ロスなど)
紙での記録や書類管理には様々な課題があります。 手書きによる記入ミスや判読困難な文字、転記作業でのヒューマンエラーなどのリスクが常に存在します。 また、紙の記録は予想以上にスペースを取り、介護記録は5年間の保管期限があるため、保管スペースの確保も大きな課題です。 さらに、過去の記録を検索・参照する際の手間や、複数のスタッフ間での情報共有の非効率さも問題となっています。
ペーパーレス化の現在地:どこまで進んでいる?
タブレットや記録アプリの導入状況
現在、介護現場ではタブレットやスマートフォンを活用した記録システムの導入が進んでいます。
厚生労働省の調査によると、介護ソフトの導入率は67.5%に達しており、その中でもクラウド型が70.3%、オンプレミス型が27.0%と、インターネットを経由してアクセスするクラウド型が主流となっています。
また、介護記録アプリも多様化し、食事や排泄の介助、リハビリテーションなどの日々の介護内容や利用者のバイタルサインなどをリアルタイムで記録できるものが増えています。
ただし、現場でのデジタル機器活用には格差があり、「介護のコミミ」チームの調査によれば、介護記録の電子化ができている事業所は50.1%に留まっています。
つまり、約半数の事業所ではまだ紙媒体での記録が主流という実態があります。
クラウド型介護ソフトの普及
クラウド型介護ソフトは、その利便性から急速に普及しています。
インターネット環境さえあればどこからでもアクセスできる利点があり、タブレットやスマートフォンからも利用可能です。
初期費用が抑えられるため導入のハードルが低く、法改正時の更新も自動的に行われるという利点も普及を後押ししています。
事例紹介:先進的な施設での取り組み
先進的な施設では、介護記録の電子化だけでなく、AI技術を活用した記録システムも導入されています。
例えば、話した言葉がそのまま文字になる音声入力機能や、登録された利用者情報をもとにしたAIによる予測結果・サービスプラン提案など、最新技術による業務効率化が実現しています。
また、バイタル機器との連携により、測定データが自動的に記録されるシステムや、異常値があった場合に自動的に警告を表示する機能なども登場しています。
これらの取り組みにより、記録業務の大幅な効率化と同時に、ケアの質の向上も実現しています。
中小規模事業者の現実とギャップ
しかし、最新技術を導入できる施設がある一方で、中小規模の事業所ではペーパーレス化が進んでいない現実もあります。
PR TIMESの調査によると、介護関連事業経営者の76.7%が「ペーパーレス化」の重要性を実感している一方で、約8割の企業は「十分にペーパーレス化できていない」と回答しています。
その主な理由として、「現状の業務で手一杯になっており、ペーパーレスを進める余裕がない」(50.0%)、「システム導入の予算がない」(30.6%)などが挙げられています。
導入を進める上での課題とハードル
現場職員のITリテラシー
介護記録の電子化を進める上での大きな課題の一つが、現場職員のITリテラシーの問題です。
厚生労働省の「ICT導入支援事業 令和3年度 導入効果報告取りまとめ」によると、「パソコンやソフトに対する職員の苦手意識の解消、職員への研修等」に課題があると感じている事業所は89.5%に上ります。
特に経験豊富なベテラン職員ほど紙媒体での記録に慣れており、デジタル機器への抵抗感が強い傾向があります。
デジタル機器に慣れていない人にとって、新しいルーティンへの変更は心理的にも身体的にも大きな負担となります。
導入コストと設備投資の壁
ペーパーレス化を進める上でのもう一つの大きな障壁が導入コストです。
システム導入のための費用には、介護ソフト自体の費用だけでなく、パソコンやタブレット、スマートフォンの購入費用や通信費も含まれます。
厚生労働省の調査では、パソコンやソフト、システムなどの導入のための費用補助について、89.8%の事業所が課題と感じていると報告されています。 特に中小規模の事業所にとっては、このような初期投資がペーパーレス化を躊躇させる要因となっています。
セキュリティと個人情報保護への不安
介護記録には利用者の健康状態や生活状況など、センシティブな個人情報が多く含まれています。 そのため、電子化に伴うセキュリティリスクや個人情報保護に関する不安も導入の障壁となっています。
クラウド型の介護ソフトは、インターネット環境とデバイスさえあればどこからでも使用できる反面、情報漏えいのリスクが高まる懸念があります。
そのため、セキュリティ対策を徹底したシステム選びと、使用する職員のセキュリティ意識の向上が重要となります。 プライバシーマークを取得し、暗号化された通信を提供するなど、セキュリティ面に配慮したサービス選びも進んでいます。
ペーパーレス化がもたらすメリット
業務効率化とケアの質向上
介護記録の電子化による最大のメリットは業務効率化です。
紙の記録を手入力する作業がなくなり、検温や排泄、食事や入浴の状況等を現場でその場で入力して直接介護ソフト側に反映できるため、記録は正確かつ効率的になります。
チェック機能を搭載している介護ソフトも多く、月末の確認作業の時間も短縮できます。 こうした間接業務の効率化により、利用者へのケアに充てる時間が増え、サービスの質向上にもつながります。
情報共有のスピードと正確性
ペーパーレス化のもう一つの大きなメリットは、情報共有の効率化です。 令和3年度の「ICT導入支援事業」を受けた事業所の多くが、スタッフ間でのスムーズな情報共有が実現したと報告しています。
電子化された記録はリアルタイムで共有でき、手書きの場合に発生する「文字が見にくい」という問題も解消されます。 これにより、チームケアの質が向上し、利用者への一貫したサービス提供が可能になります。
記録の見える化とエビデンスの強化
介護記録の電子化によって、データの活用が容易になります。
電子化された記録は検索や分析が簡単で、利用者の状態変化の傾向把握やケアの効果検証が可能になります。 これにより、根拠に基づく介護(エビデンスベースドケア)の実践が促進され、介護の質の向上につながります。 実際に、介護記録の電子化を行った施設では、7割近くが根拠に基づく議論・意思決定が実現したと報告しています。
今後の展望とAI・DXとのつながり
音声入力やAI記録支援ツールの登場
介護現場のペーパーレス化は、AI技術との融合によってさらに進化しています。 話した言葉がそのまま文字になる音声入力機能や、ネックスピーカー型デバイスを活用した「しゃべるだけ」の記録入力システムなど、記録業務の負担を劇的に軽減する技術が登場しています。
また、AIによる予測結果やサービスプラン提案など、判断支援機能も充実してきており、こうした技術の進化が介護現場の業務効率化をさらに加速させることが期待されています。
データ活用による予防ケア・リスク管理
電子化された介護記録からのデータ活用も進んでいます。 バイタル情報のグラフ化や提供サービス内容の分析・統計など、蓄積されたデータを活用することで、予防ケアやリスク管理の高度化が可能になっています。
例えば、バイタル異常があった際の自動警告表示や、服薬や入浴といった重大なリスク場面での管理支援機能など、安全なケア提供をサポートするツールも充実してきています。 これらのデータ活用は、個別ケアの質向上だけでなく、施設全体のサービス改善や経営判断にも役立てられています。
DX全体の流れの中でのペーパーレスの位置づけ
介護現場のペーパーレス化は、介護業界全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)の一環として進められています。
単に紙をデジタルに置き換えるだけでなく、業務プロセス全体の見直しや、介護ロボットやVRなどの新技術導入も含めた包括的な改革が進行中です。
厚生労働省も「介護現場における多様な働き方導入モデル事業」を実施するなど、テクノロジーを活用した働き方改革を推進しており、ペーパーレス化はその基盤となる重要な取り組みとして位置づけられています。
まず何から始めるべきか?
小さく始めて段階的に進める方法
介護記録の電子化は一度にすべてを変えるのではなく、段階的に進めることが成功の鍵です。 ペーパーレス化の対象を区切って、職員が慣れやすい業務から始めるのがおすすめです。
いきなりすべての業務をペーパーレス化すると、慣れない作業ばかりに職員が混乱してしまう可能性があります。
例えば、まずは日々の介護記録から電子化し、慣れてきたらケアプランや請求業務へと拡大していくアプローチが効果的です。
導入時に押さえるべきポイント
介護記録の電子化を成功させるためには、まず課題を明確にすることが重要です。 「電子化したらかえって手間が増えた」という失敗を避けるためにも、そもそも解決したい課題は何かを明確にし、その課題解決に適したシステムを選ぶことが大切です。
また、導入前に職員への十分な研修を行い、操作方法だけでなく電子化のメリットについても理解を促すことで、現場の抵抗感を減らすことができます。 さらに、使いやすさを重視したシステム選びも重要です。
特に介護現場では持ち運びやすさが重要なため、タブレットよりもスマートフォンが適している場合もあります。
現場と経営層が一体となる取り組みを
介護記録の電子化を成功させるためには、現場職員と経営層が一体となって取り組むことが不可欠です。
経営層はコスト面や将来的なビジョンを示し、現場の意見を尊重した上で導入を進めることが重要です。 また、ITに詳しい人材の確保や育成も成功の鍵となります。
既に事業所内にパソコンやICT機器に詳しい人材がいれば問題ありませんが、いない場合はITスキルを持つ人材を採用したり、育成したりすることも検討すべきです。
まとめ
介護業界のペーパーレス化は、2025年問題を目前に控えた今、避けては通れない課題となっています。
約30万人の人材不足が予測される中、業務効率化とケアの質の向上を同時に実現する鍵として注目されています。
導入には現場のITリテラシーやコスト面での課題もありますが、小さく始めて段階的に進める方法や、現場と経営層が一体となった取り組みによって乗り越えられます。 さらにAI技術との融合により、単なる記録の電子化を超えた業務改革へと発展しつつあります。
介護現場のペーパーレス化は、介護の質を高め、働き方改革を実現する重要な一歩と言えるでしょう。