介護施設では、転倒や徘徊、急な体調の変化など、**「見守り」**が非常に重要な役割を果たします。これまで主に人の目によって担われていたこの仕事に、いま、AIカメラという新たなテクノロジーが加わりつつあります。
「見張られているようで利用者が嫌がるのでは?」
「AIに頼って本当に安心できるの?」
「プライバシーやコストはどうなの?」
そうした疑問の声もある中で、すでに複数の施設ではAIカメラが導入され、一定の成果と信頼を得始めているのも事実です。
この記事では、AIカメラとはどんなものなのか、どのように役立っているのか、導入事例や課題を含めて詳しく紹介していきます。
AIカメラとは?従来の監視カメラとの違い

単なる“映像記録”ではない
AIカメラとは、映像をただ録画するだけの従来型防犯カメラとは異なり、映像データをリアルタイムで解析し、異常や特定の動作を検知するカメラシステムのことを指します。
介護施設で導入されているAIカメラには、以下のような機能が備わっています。
主な機能:
- 転倒や倒れ込みの自動検知
- 徘徊や異常行動の予兆分析
- 一定時間動きがない状態を感知して通知
- ベッドからの離床を検知し、職員にアラート
- 顔認証で利用者の識別が可能なものも
つまり、「人の目の代わり」になるだけでなく、「人では見逃すような瞬間」も察知できる技術として注目されています。
実際の導入事例とその効果
ケース1:東京都内の特別養護老人ホーム(定員80名)
導入されたのは、パナソニック製のAI搭載見守りカメラシステム。各個室に設置され、夜間の転倒や離床、トイレでの長時間滞在をモニターしています。
導入後の成果:
- 夜間の転倒事故が約40%減少
- 職員の巡回数を約30%削減
- 夜勤スタッフ1人の負担が大幅に軽減
現場の声:
「徘徊が多い利用者の“動き出し”をすぐに察知でき、最悪の事態を防げたことが何度もあります。」
「目が届かない時間帯に“もう一人の目”がある感覚で安心できる」
ケース2:地方の有料老人ホーム(中規模・約40名)
こちらでは、セコムのHitomeQケアサポートを導入。カメラだけでなく、マットセンサーやスマートフォン通知との連携で、見守り・介助のタイミング最適化を目指しています。
効果と実感:
- 利用者の夜間睡眠の質が向上(見回り減少による)
- 職員間の申し送りや記録の正確性が向上
- 転倒リスクのある“予兆行動”を事前に察知可能に
本当に役に立つ?現場での評価
メリット
① 事故予防
- 転倒や離床の初期動作を検知し、“事後対応”から“予防”へ
- センサーでは把握できない**動きの“質”や“流れ”**も確認可能
② 職員の負担軽減
- 常に巡回しなくても良い→時間に余裕が生まれる
- 利用者が何か起こす前に、「駆けつける判断」ができる
③ 記録の質向上・申し送りの明確化
- 映像に基づいた事実確認ができ、曖昧な情報の共有が減少
- 「いつ、どこで、なぜ起きたか」が明確に
導入の壁と課題は?
① プライバシー問題
「24時間カメラで見られている」ということに対して、利用者本人や家族が抵抗感を持つケースは少なくありません。
対応策:
- 映像の録画保存は限定し、リアルタイム解析のみに利用
- 家族との事前説明・同意取得の徹底
- トイレ・脱衣所など撮影範囲を明確に制限
② コストの問題
- カメラ1台あたり10万円〜30万円程度
- システム全体で数百万円の投資になることも
対応策:
- 国や自治体による補助金制度の活用
- レンタル・サブスクリプション型サービスの選択
③ 技術への不慣れ
高齢の職員やITリテラシーが低い人にとっては、カメラ操作やシステム管理がハードルになることも。
対応策:
- 直感的なUIの導入
- 導入時の丁寧な操作研修とマニュアル整備
今後の可能性と展望
AIカメラ×ビッグデータで「行動傾向」も可視化
- 転倒リスクの高い動き(例:ふらつき、傾き)を事前に検知
- 利用者ごとの“行動履歴”を学習し、個別リスクを数値化
- ケアプランや職員配置の判断材料にも活用可能
他のAIツールとの連携も進化中
- 見守りカメラ+排泄センサーの統合
- 音声解析による異常音(叫び声、転倒音など)の検知
- スマートフォンとの連携でリアルタイム対応がより迅速に
まとめ:AIカメラは“人を減らす”ためではなく、“人を支える”ために
AIカメラは、決して「職員の代わりにすべてを行う装置」ではありません。
むしろ、職員の目が届かない“スキマ”を補う補助的存在として、現場で着実に効果を発揮しています。
- 転倒事故の予防
- 夜間見守りの効率化
- 申し送りや報告の精度向上
それらはすべて、人とテクノロジーが協力してこそ実現できる成果です。
導入にあたっては、コストやプライバシーといった課題もありますが、ひとつずつ丁寧にクリアしていくことで、より安全で効率的な介護の現場が築かれていくでしょう。
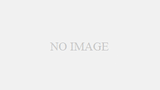
コメント